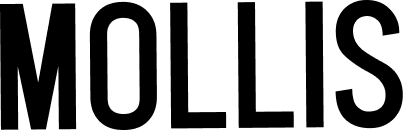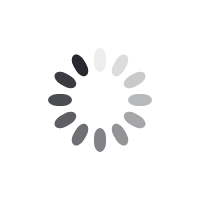独自の視点でセレクトされた植物を取り扱う「叢(くさむら)」の代表であり、 今回MOLLISの監修を手掛けてくださった小田康平さん。 海外放浪、世界的アートコレクターとの出会い、植物と自分との向き合い方――。 紆余曲折を経て今や世界的に評価されるまでになった 小田さんの植物にまつわるストーリーを前編・後編に分けてお届けします。

子どものころに感じた幸せのアイコン
――まずはこの業界に入るきっかけから聞かせてもらってもいいですか?
実は実家が花屋なんです。でも、子どものころは花屋ではなく、税理士になりたかった。小学校6年生のときにはすでにその夢を思い描いていて、20歳ぐらいまでは「絶対に税理士になるんだ!」とまで思っていました。
――なぜ税理士になりたかったのですか?
うちの父親はとにかく忙しい毎日を送っていました。その割には貧乏で、お金とは無縁の生活でした。でもお金持ちの友達の家を見ると、休日になると当たり前のように犬の散歩をしていて、忙しさとは無縁の世界。「何か違うぞ? 忙しいことがお金につながるんじゃないんだな」と子どもながらに思ったわけです。ちなみその子のお父さんは税理士で、税理士には算数が得意な子がなると聞き、「あ、僕も得意だ。じゃあ税理士になろう!」と(笑)。
――とてもストレートな発想ですね。
子どものころは「大きい家、お金持ち、犬」といった分かりやすいアイコンに対して「幸せ」を感じていたんでしょうね。
――それがなぜ今の職業に?
税理士になるという目標はずっとありました。中学、高校、大学ともにまあまあいいところに入って、成績もそこそこ。でもそれは裏を返せば、中途半端。そんな状況でがんばったとしても、僕の代わりはいくらでもいる。要は今の自分にはパンチが足りないことに気付いたんですね。でもパンチってどうやって得るんだろう……と考えた末に思いついたのが海外でした。それまで一度も海外に行ったことがなかったんです。海外にいくと『北斗の拳』みたいな世界が広がっていて、荒波に揉まれれば自分も強くなれるのではと思ったんです(笑)。

――若者らしいですね(笑)。行き先はどちらでしたか?
大学でスペイン人の先生の知り合いがいて、その人に見せてもらった小麦畑の写真がキレイだったから、じゃあスペインに行こうかと。大学を卒業するちょっと前だから、22歳のときです。税理士への夢は20歳ぐらいに諦めていたので、就職活動はまったくしませんでした。スペインにいってもノープラン。まずは1年、アルバイトで貯めたお金がなくなるまでいようと思っていました。
――本当に行き当たりばったりですね。
スペインについて向かったのが、バルセロナ。食べ物は美味しい、建物もきれいですごく平和な時間でした。でもここでまた…
――パンチがたりない?
そう。当時の僕は平和を求めてスペインにきたわけじゃない。それでどこか違うところに行こうということになったんですが、たまたま会った日本人に見せてもらったサハラ砂漠の写真に感動して、モロッコに向かってみようと。ジブラルタル海峡を渡ってモロッコに入った瞬間、人の波に圧倒されました。「お金くれ」とせがまれたり、「宿こっちだぜ」と騙そうとするやつがいたりして、とにかくものすごいエネルギー。国境を超えることの楽しさを覚えて、中東、ヨーロッパ、東欧など1年間色んな国を回りました。

パリのインテリアショップでの出会いが人生を変える
――しばらくバックパッカーをされていたんですね。
もともとインテリアとか雑貨が好きだったので、イギリスやフランスにも時間があれば立ち寄ったりしました。そんな折、パリの街角を歩いていたらとあるインテリアショップに目が留まりました。ショーウィンドウの前に立って、「そうじゃない、もうちょっとこっちだよ」みたいなことをやっているスタッフがいたんです。次の日にいっても同じ光景が広がっていたんですが、偉い人なのかなんなのか、とにかく空間を制圧している感じがあったんです。
――その人は何をされていたんでしょう?
花屋だったんです。でも僕が知っている花屋とはまったく違いました。シュッとしていてものすごく輝いて見えた。「あ、僕のやりたかったことはこれだ」と直感的に思いましたね。日本に帰ったらこれを仕事にしようと。

――運命的な出会いだったわけですね。
空間をつくるためには、建物がいる、内装がいる、インテリアがいる、音楽、照明……とあげたらキリがない。全部一流になったらすごいと思いましたが、全部に手を出したら時間が足りない。だからそのなかのひとつでも一流になれればいいと考えたんです。得意かどうかはさておき、植物は僕が小さいころから慣れ親しんできたものだから、「植物」なら勝てるんじゃないかって。
――それで地元の広島に帰られたんですか?
そうです。独学で勉強して、そういう仲間も少しずつできて空間づくりの仕事ももらえるようになってきました。でも、そこでまた僕の中で“違和感”が生まれたんです。
――違和感……?
建築、内装、照明、植物が混ざり合うことで“いい空間”はできるんですが、3日も経てば植物だけが枯れてしまう。僕がどれだけカッコいい空間づくりに寄与したとしても、1週間後にはゴミになってしまうんです。
――そう考えると切ないですね。
植物としての儚さは僕も理解していますが、切られて死んでいく植物より、土がついて生きていく植物がいいとそのとき感じましたね。市場に買い付けに行ったりもしましたが、「これだ!」と思って競って手に入れた植物も、翌週にも同じものが売りに出され、別の花屋やホームセンターに置かれるようになる。面白い植物を手に入れても、結局は大量生産だから産地にいけば山ほどあるわけです。
――そこでもまた違和感?
そうです。だから生産地にいけば市場のフィルターが入っていない植物があるのではと思い全国行脚をはじめました。それが今のスタイルにつながっていくわけです。鹿児島にいくと巨大なハウスがあって探し放題。でもそこに並んでいるのはどれも同じ顔をした植物ばかりでした。それでもあきらめず、棚の下とかハウスの横とか裏とかまで探して、僕の求める植物を1つ1つ買い付けていきました。自分の目利きで植物を探し出す。他人には無価値かもしれないけど、僕にとっては宝探しだったんです。

どれだけいいものをつくっても伝わらなければ意味がない
――そのころから多肉植物がメインだったのですか?
当初は観葉植物がメインでしたが、もっといろんな表情を持つ植物を扱いたいと思い、多肉植物に切り替えていきました。全国に趣味でサボテンを作っている達人がたくさんいてその人たちから買い付けるというスタイルを確立したのもこのころですね。
――自分のお店を立ち上げたのはいつでしょう?
8年前です。ネイルサロンに納品したらそこのお客様がとても気に入ってくださって、「持ちビルがあるからそこでやらないか」と声をかけていただいたんです。
――何か光るものを見つけたのでしょうね。
「お兄ちゃんがどんなにいいものつくっても、それが伝わらないと意味がない」というようなことを言われました。当時、実家の花屋にいたんですがそこにいたらダメだと。物件を見せていただき、お金もないのに「やります!」と。またここでも行き当たりばったり(笑)。
――お店はすぐに軌道にのったのでしょうか?
その年、開店して初めてのクリスマスだったので、リースを100以上つくって飾りました。それまで働いていた親のお店ではこういうこともできなかったし、奥に長い店だったので。そんなある日、世界的に有名なアートコレクターの方が偶然いらして、店先に置いてあった多肉植物に興味を示されたんです。
――どんな反応でしたか?
僕が丁寧に説明したら、この価値観は面白いと評価してくれたんです。このときですね。叢の方向性が定まったのは。さらにその方がどんどんお客さんを紹介してくださって、どんどん人脈が広がっていきました。
――漫画のストーリーのようですね。
ひとつひとつの仕事をきちっとこなして喜んでいただき、それが次につながるというわらしべ長者的な感じでした。当時、植物の個性に特化した植物屋なんてまったくなかったから、「いける」という、根拠のない自信だけはありました。次の一手が、東京での個展開催。サボテンをギャラリーのような場所で鉢植えで販売するという方法は、おそらく日本ではありませんでした。これをやれば絶対に分かってくれる人がいるんじゃないかって。結果的に、大ヒットしたんです。
――そんなに売れたんですか?
期間は一ヶ月ちょっとでしたが、500個ぐらいがあっという間になくなったんです。冬にもう一度やったんですが、ギャラリーに届いた段ボールを開けるたび、売れていくような状況でしたから。
>>後編はこちら

PROFILE
小田康平
1976年、広島生まれ。大学在学中に海外を放浪したのち、フランスでの出会いをきっかけに植物を軸とした空間デザインを手掛けるように。2012年に独自の美しさを提案する植物屋「 叢 - Qusamura 」をオープンさせ、2019年には東京進出。国内はもとより海外からも評価が高く、様々なジャンルのアーティストたちとのコラボレーションも積極的に行うほか「MOLLIS」の監修も手掛けている。